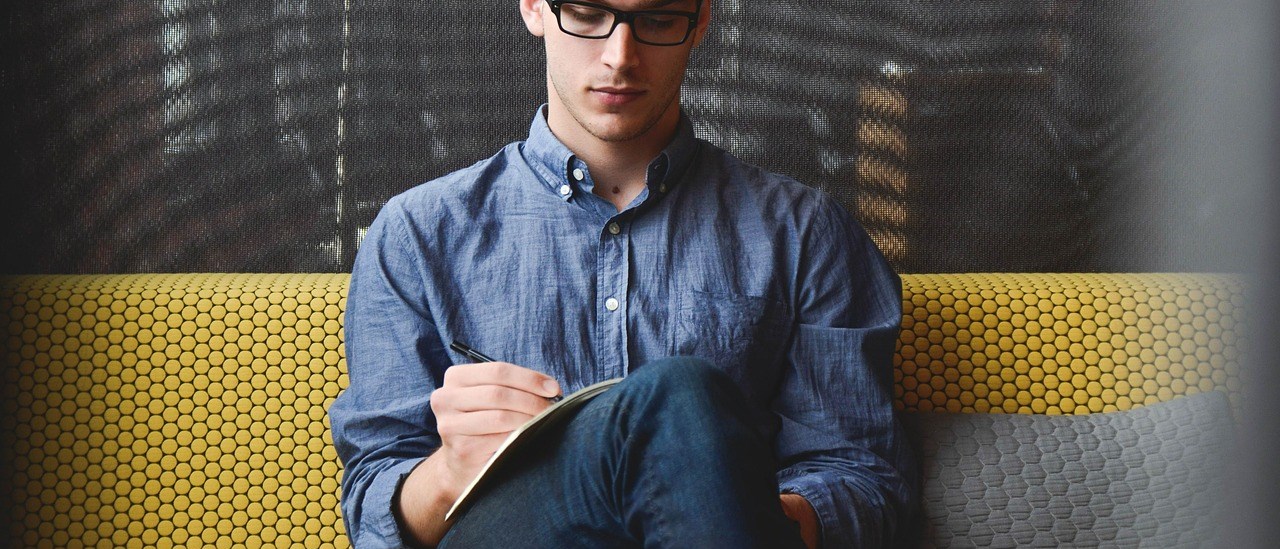こんにちは。
神奈川県大和市の印刷・企画・デザインならおまかせのアドタックです。
私たちは日常の中で「赤いリンゴ」「青い空」といった表現を当たり前のように使っています。
信号の色も、子どものころから「赤は止まれ、青は進め」と自然に覚えてきました。
でも実は、この「赤」や「青」という色の区分けや呼び方は、世界中で一律ではなく
時代や文化によってかなり違いがあるということをご存じでしょうか?

青という色は“新しい”?
日本語で「青」は、もともと緑を含んだ広い意味を持っていました。
今でも「青リンゴ」「青菜」と言えば緑色のものを指しますし、「青信号」はどう見ても緑ですよね。
これは昔の日本語に「緑」という言葉が独立して存在しにくかった名残だと考えられています。
一方、ヨーロッパの古代文学にも面白い例があります。
古代ギリシャの叙事詩『オデュッセイア』には「葡萄酒色の海」という表現が登場します。
現代人なら“海は青い”とすぐに思いますが、彼らにとって海は「青」とは別のニュアンスで
捉えられていたようです。
人類が「青」という色を明確に区別するようになったのは比較的近代になってからだとも
言われています。


赤は“最古”の色
一方で「赤」はどの文化でも非常に早く言葉として存在していたようです。
血や火、太陽のように人類にとって重要で強烈な存在が赤だったため、
言葉として早い段階から必要とされたと考えられているようです。
赤は危険や警告を示す色として世界中で共通しやすく、
現代の交通標識や警告表示にも受け継がれています。
逆に青は自然界であまり見られない色(空と水くらい)だったため、
言葉として必要とされるのが遅かったのかもしれません。


色の境界は文化次第
「赤」と「青」をどの範囲に含めるかは、文化や言語によって異なります。
たとえばロシア語には「青」と「水色」を区別する別々の単語があり、
日本語の「青」の概念とはズレがあります。
逆に英語では“green light”と呼ぶ信号を、日本語では「青信号」と呼ぶという違いも。
つまり、色そのものの見え方は人間の目の仕組みとして共通でも、
その区切り方や言葉は文化に強く影響されるのです。


デザインの現場での“赤と青”
印刷やデザインの現場でも、「赤っぽい青」「青みがかった赤」といった表現はよく登場します。
実際にはCMYKのわずかな調整で、印象はがらりと変わります。
ある人にとっては「青」に見える色が、別の人には「緑っぽい」と感じられることも
珍しくありません。
だからこそ、デザイナーや印刷に携わる人は“言葉のズレ”を埋めるために、
カラーチップや色見本を使って正確な共通認識を作るのです。
「赤」と「青」という基本的な色ですら、世界共通の定義ではない――その事実を知っていると、
色のやりとりに少し慎重になれますし、色彩をめぐる文化の奥深さに気付かされます。

終わりに
「赤」は古代から特別視されてきた色であり、「青」は比較的“新しく生まれた色名”。
私たちが日常で当たり前に使っている色の言葉も、歴史をたどると必ずしも世界共通ではありません。
文化ごとの違いを知ることで、印刷やデザインの仕事の中でも「色」をより豊かに理解し、
表現できるのではないでしょうか。
〈N.M〉